| 明治その1 1868年 明治元年9月〜 | |
| 9月 | 年号を明治と改元 |
| ちょっとまとめ | |
| 9月20日 | 明治天皇 東京へ |
| 東京に行くまでのてんやわんや | |
| 天皇って何???by庶民 | |
| 大鳥圭介・土方歳三の状況 | |
| 榎本武揚の状況 | |
| 仙台藩降伏 | |
| 10月12日 | 榎本武揚、蝦夷地へ向かう |
| 10月20日 | 旧幕府艦隊 渡島半島へ |
| 箱館府大慌て!! | |
| 10月21日 | 旧幕府脱走軍の使者 箱館府へ |
| 10月22日 | 人見 夜襲を受ける 峠下の戦い |
| 箱館戦争 | |
| 大野・文月の戦い | |
| 七里の戦い | |
| 10月25日 | 清水谷ら逃亡 |
| 10月26日 | 旧幕府軍 箱館を占領する |
| 松前藩 使者を斬り捨てる | |
| 10月28日 | 土方 松前へ向かう |
| 11月1日 | 土方 松前藩を蹴散らす |
| 11月5日 | 松前藩 落城 |
| 松前藩主 逃げちゃいました | |
| 土方軍 江差をゲットする | |
| 11月15日 | 江差湾で軍艦 開陽丸が座礁する |
| 英仏 「デ・ファクトの政権」 | |
| 12月15日 | 蝦夷政権誕生 |
| この年の主な出来事 | |
| 明治時代その1 1868年 明治元年9月〜 |
| 9月 年号を明治と改元 |
ずーっと続いた「江戸時代」が幕を閉じました ここからは「明治時代」へと突入します あ、そうそう「明治維新」というのは、ワタクシの中では王政復古の大号令〜廃藩置県までを言いマス ちなみに、江戸っ子らは「明治」を下から読んで「治まるめい」と笑ってました 明治時代は日本が世界へと進出していく時代でもあります 今まで日本はずーーーっと鎖国を続けており、外国の船がやってきても全て拒否していました その間、世界は動いていたのです 思いっきり国際化社会に取り残された日本は、明治時代で一気に上へ上へと這い上がってくるのです さて、ここハガクレ★カフェでも、これからは「世界の動向」も見逃すことは出来なくなってきました これからは世界史分野もこちょこちょと取り入れて日本を紹介していきたいと思っております |
| ちょっとまとめ |
会津が開城し、もはや幕府側は終わったかと思いきや、まだ新政府に牙を向く人たちがいました 幕末その16では会津藩中心となったため紹介できませんでしたが、まだ幕府のために戦っている人たちがいたのです 中心人物となるのは、榎本武揚・大鳥圭介・土方歳三の三人 お話はちょっと前後しますが、ここでは彼らが会津戦争の間どうしていたかもちょっと紹介します できれば、幕末その16までを読み、理解できている方の方がスムーズに読めると思いますよ〜 |
| 9月20日 明治天皇 東京へ |
 会津陥落が決定的となり、明治天皇は行幸として江戸へ向かいました ちなみに7月17日に江戸を「東京」と改称しておりました 「東の都(東京)」という意味であります そして江戸城は東京城と改められ、皇居となりました ちなみに天皇は江戸へ行きましたが、「遷都(都を変えること)」をはっきりと明言していないため、京都では天皇は江戸に下がっただけで、実際の天皇の住まいは京都だという考えが残っております |
| 東京に行くまでのてんやわんや |
徳川慶喜が大阪から江戸に逃げ帰った頃、大久保利通&岩倉具視は新政府確立のために色んなことをしておりました 戦いは戦い屋に任せて、大久保らは政府の仕組みなどなどを考えていたのです はじめ木戸孝允(桂小五郎)は首都を大阪にしようと言っていました が、大久保が提案したのは「江戸」だったのです 大久保の考えは「この出来事は今までに無い未曾有の出来事。ありきたりの対応じゃダメだ。戦いは新政府が勝利し、賊軍(幕府)は敗走したけど、敵の本拠地である江戸はまだまだ大人しくなしていないだろう。 それに天皇が今までどおり京都にいたら、また雲の上の人 これから、天皇というのは国民の「親」となっていかなければならない 天皇が政治の中心とならなければならないのに、いつまでも朝廷の御簾の中に隠れている人であってはならない」 こういった考えだったのです が、朝廷は大ブーイング!! 「天皇は京都にいなければならない!朝廷というのは京都にあるべきものなのだーー!!」と騒ぎまくり さらに大久保とつるんでるのが岩倉具視ってのもおもしろくない 今までビンボー公家だった岩倉具視がいきなり政治の中枢に入り権力を握ってるのがおもしろくない人がいっぱいいたのです が、江戸では彰義隊だのなんだのと、まだまだ騒然としていた このまま京都でぼんやりしているわけにはいかない!!ということとなり、公卿の反対を押し切り天皇は江戸へ行くこととなったのです |
| 天皇って何???by庶民 |
 ところで、庶民にとって天皇というのはめっちゃ遠い存在でした 今までずーっと徳川時代が300年も続いていたので、「天皇」という存在を知らない人もたっくさんいたのです ということで、天皇とは天照(アマテラス)の子孫であるということを宣伝するようになっていきます 維新の政府は、以後日本各地で「本来日本という国は天照大神の子孫である天皇のものなんです」という教育をしていくことになり、今まで幕藩体制が続いていた日本に新たな意識を教え込んでいくのでした |
| 大鳥圭介・土方歳三の状況 |
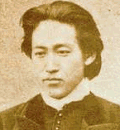 大鳥圭介といえば、江戸城が開城した後すぐに伝習隊を率いて江戸を脱出しました その後どうしたか??というと、現在の千葉県市川市あたりに続々と旧幕府軍が集まっていたのです もちろん大鳥圭介らもそこに集まりました そこには、流山で近藤と別れた後の土方歳三や会津藩の秋月登之助、桑名藩士の辰巳勘三郎など、新政府軍に対して反感を抱いている人たちが沢山集まっていたのです そして大鳥圭介と土方歳三は今後盟友となっていきます さて、彼らはまず徳川ゆかりの地、日光を目指しました ここに拠点をもうけ、世の動きを観察しながら動くことを決めたのです 三手に分かれ、日光へ向かうことになりました 土方は会津藩の秋月登之助とともに先発隊を統率し日光へ向かいました 途中宇都宮にて怪我をしてしまい、戦線離脱し傷の療養に専念することになります その間に時代は動いていきます 江戸が無血開城してしまったため、新政府軍は大きな戦いをすることなく江戸をゲット せっかく戦による恩賞を期待していた兵たちは不満 新政府としても彼らの不満のぶつけ場所が必要だったし、新政権の威信を天下に示すためにも何か戦いが必要だった その生贄に選ばれたのが、かつて新撰組を率いて京都にてさんざん薩長らを苦しめた会津藩だったのです 新政府軍は将軍家から会津藩に矛先をかえることに が、東北諸藩はそれが気の毒で「会津を許してあげてほしい」ということに かくして、奥羽越列藩同盟ができあがり、東北の諸藩は新政府軍と戦うことになったのです もちろん、大鳥圭介らも戦います 大鳥は5月1日の白河城攻防に参加しますが、結局破れ会津領へと引き上げていきます 7月始めにやっと怪我が治った土方は会津へ向かいますが、この頃には奥羽の諸藩は新政府軍に負けまくっていました それでも大鳥・土方の二人は、新撰組・伝習隊・回天隊などを率いて新政府軍と戦いました が、戦いは負け続き 土方は援軍を求めに仙台藩へ向かったのです |
| 榎本武揚の状況 |
 榎本武揚は、幕臣としてのけじめをつけるべく、慶喜の処罰が決まるまで一切江戸を動きませんでした 榎本武揚は、幕臣としてのけじめをつけるべく、慶喜の処罰が決まるまで一切江戸を動きませんでしたやっと動き出した頃には、もはや奥羽の諸藩のほとんどが新政府軍に降伏していました そんな榎本武揚には考えていたことが 「将軍家が七十万石という一大名レベルになってしまった。これでは今までの幕臣たちを養っていくことはできない、そのために、広大な未開拓地である蝦夷に旧幕臣たちを移住させたい」というもの こうして榎本は新政府軍にこの意見を徳川亀之助の名を持って願い出ました 「譜代家臣の多くが、今までどおり徳川に仕えたいと言っています。が、この状況ではとうてい彼らを養うことはムリです。かといえって、朝廷へ援助してくれというのも恐れ多い。ですが彼らをクビにしてしまえば、多くの人が路頭に迷い、餓死してしまいます。それは徳川にとって不憫でなりません。そこで徳川に仕えたい者たちを蝦夷地へ行かせたいと思います。開拓によって、生きていく道も開けるでしょう」 が、返事はNO 新政府は遠い蝦夷地に行かれ、勝手なことをやられたら困るからです そしてとうとう榎本武揚は、莫大は軍資金を積み、開陽・回天などの四つの軍艦に、四つの送船を伴い江戸を出て行ってしまったのでした が!!銚子にて激しい暴風雨に見舞われ、艦隊はバラバラに 大量の軍資金が海の底へ沈んでしまったのです それでもなんとか六隻は残り、仙台藩へ向かったのでした |
| 仙台藩降伏 |
旧幕府艦隊が停泊している仙台藩ですが、もはや超弱気になっていました 九月に入って会津方面の戦況がまずくなってくると、仙台城下にぞくぞくと旧幕府勢力が集まってきたのです もちろん「会津が破れたら、仙台が最後の砦になるであろう」と、皆思っていたからです ところが!仙台藩のおエライさんたちは、もはや勝ち目はないだろうと、降伏の意思をあらわし始めました 仙台に集結していた榎本武揚や土方歳三らは必死で徹底抗戦を説得しましたが、とうとう降伏を決意したのです 仙台藩が降伏したことにより、奥羽諸藩は一気に戦意喪失 そして、幕末その16に書いたように、会津藩も落城し、もはや本州に彼ら(旧幕府の人たち)の居場所はなくなってしまったのです |
| 10月12日 榎本武揚、蝦夷地へ向かう |
 もはや、旧幕府軍のいる場所はない もはや、旧幕府軍のいる場所はない榎本武揚は、そんな絶望の淵にいる彼らを励まし、艦隊に乗船させ、ともに蝦夷地を目指すことにしたのです 榎本らは仙台藩が降伏してから、ずっと暴風雨で壊れた船の修理をしておりました そして何とか応急処置が終わると、約3000人を乗せた艦隊が、蝦夷を目指し出発したのでした この時、榎本らと合流したのは・・・ 桑名藩主・松平定敬(まつだいらさだあき) 元老中・板倉勝静(いたくらかつきよ) 元老中・小笠原長行(おがさわらながみち) 新撰組副長・土方歳三 遊撃隊長・人見勝太郎 などなどであります |
| 10月20日 旧幕府艦隊 渡島半島へ |
この日、箱館から40キロほど離れた渡島半島の鷲ノ木湾へ艦隊が到着しました 箱館はいまや国際港(開港させられたからね)になっていたので、直接行くのはマズイと思ったのでしょう 一応、艦隊がやってきた理由は「蝦夷地に移住し、この地を開墾しながら生計を立てさせてほしい」というもの 新政府には蝦夷地開拓を嘆願する書面も出しました(もちろん、出しただけで許可は得てません) ちなみに、10月20日というのは旧暦で、新暦になおすと12月3日 北海道なので、もう雪が30センチほど積もっておりました そんな中、突然艦隊が海の向こうからやってきたもんだから鷲ノ木村の人たちはパニック状態に! みんな雪の中を飛び出し、林で身を潜めたそうです |
| 箱館府大慌て!! |
ではちょこっと箱館府のことを説明しましょー 箱館府とは、戊辰戦争が始まった時に清水谷公考(しみずだにきんなる)という人が、蝦夷地鎮撫を朝廷に出し、新政府によって派遣されました で、この清水谷が旧幕府の箱館奉行から権利を引き継ぎ、箱館府知事となったのでした 清水谷の下には、奥羽諸藩の幕臣たちが働いていましたが、奥羽列藩同盟が結成されると、みんな自分たちの藩へ戻っていってしまいました そんな中、この箱館からわずか40キロしか離れていないところに、旧幕府艦隊が到着してきたのです |
| 10月21日 旧幕府脱走軍の使者 箱館府へ |
旧幕府方脱走軍は、人見勝太郎(元・遊撃隊)と本多幸七郎(元幕臣で、大鳥圭介の右腕)の二名を使者として、兵30人をつけ箱館府へ派遣しました 彼らは「蝦夷地を徳川家臣たちの場所にしてほしい」という嘆願書を持ってやってきました その間に、大鳥圭介率いる部隊と、土方歳三率いる部隊が、二手に分かれて箱館に向かっておりました |
| 10月22日 人見 夜襲を受ける 峠下の戦い |
この日、箱館へ向かっていた人見と本多が、突然何者かによって銃撃を受けました これは清水谷の命令を受けた松前藩と津軽藩の兵たちによる夜襲だったのです 人見らはいきなり宿に銃撃されて大混乱に そこへ、駆けつけてやってきた大鳥隊の先鋒 猛者をそろえた大鳥の先鋒隊によって新政府軍はすぐさま撤退 こうして箱館での戦いの火蓋が切って落とされたのです |
| 箱館戦争 |
新政府軍が敗退した後、大鳥本隊が到着しました そして「われわれは嘆願しに行ったというのに、箱館府は夜襲を仕掛けてきた。兵を動かすのはやむをえない」と、宣戦布告したのです こうして風雪が激しい中、進軍していくことになったのです |
| 大野・文月の戦い |
大野には、新政府軍が500人ほどいました 大鳥は伝習二番隊を先発させ、別の隊を迂回させ、自らは本多幸七郎とともに三隊を率いて大野へ近づいていきました まもなく、伝習二番隊が敵と接触し、銃撃戦が すると大鳥らもすぐさま戦闘開始 が、新政府軍はあっけなく五稜郭方面へ敗走していったのです さらに、大野から近い文月(ふみつき)という場所に、新政府軍がいるという情報を聞くと、すぐさま向かいました 旧幕府軍が現れると、新政府軍は慌てて逃げていきました こうして、旧幕府軍は敵の大砲や食料を確保することもできたのでした |
| 七里の戦い |
あっけないほどの勝利を得た旧幕府軍でしたが、七里では激戦が予想されました 七里という場所は、箱館五稜郭に通じる重要な拠点なので、新政府軍も何とかしてこの場所は死守しなければならなかったからです 新政府軍の大将は、長州藩の堀真五郎で、吉田松陰の松下村塾で学び、高杉晋作らと共に行動していた人でした 歴戦の志士だったので、旧幕府軍の人見隊は絶体絶命の危機におちいるほど が、元新撰組の人たちが応援にかけつけ、戦いの流れが変わりました すると人見ら遊撃隊のメンバーたちも、がぜんやる気を出し、最後は一丸となって新政府軍に突撃 こうして何とか、旧幕府軍は勝利をつかんだのであります |
| 10月25日 清水谷ら逃亡 |
五稜郭では、味方の敗北ニュースが次々とやってきました 「このまま籠城しても、今は厳しい冬のど真ん中。新政府からの援軍は期待できない」 ということで、箱館府のお偉いさんたちは、五稜郭を脱出し、翌日、箱館港から逃亡したのであります 箱館府のお偉いさんたちが逃げてきたことを知った津軽藩兵らも、みな逃走していきました |
| 10月26日 旧幕府軍 箱館を占領する |
さて、大鳥や人見が率いる旧幕府軍は、五稜郭目指して進軍開始 が、五稜郭はもぬけの殻 旧幕府軍はなんなく五稜郭をゲットしたのでした ちなみに・・・、清水谷らが逃げた後すぐに盗賊が五稜郭内に入り込み、さまざまな道具を盗まれました 旧幕府軍がやってきた時は、かなりひどい有様になっていたのでした そして、この日の夕方別同部隊の土方歳三らも五稜郭に到着 土方らは戦闘をほとんどしないまま、五稜郭に到達したのでありました さらにこの日、箱館港には、旧幕府艦隊が入り込み、港と市街も制圧 完全に旧幕府軍が占拠したのであります こうして、旧幕府軍は蝦夷地へ到達してからあっという間に占拠し、ここ五稜郭を拠点にすることを決めたのでした |
| 松前藩 使者を斬り捨てる |
松前藩は、旧幕府軍が蝦夷地にやってくる三ヶ月前、新政府に降伏していました 旧幕府軍が鷲ノ木に到着した時も、松前藩は五稜郭へ進軍してくる旧幕府軍を阻止するべく主力となって戦っていました が、肝心のお偉いさんたちが五稜郭から逃げてきてしまい、松前藩のみが唯一の新政府勢力となってしまったのです 五稜郭を占拠した旧幕府軍は、松前藩の福山城へ使者を差し向けました 「松前藩はかつて老中をしたこともある家柄。恨みもなければ争いもしたくない。共に力を合わせて蝦夷地を開拓しよう」と、考えていたのです そして、箱館戦争の時に捕虜にした松前藩士の桜井を使者にし、福山城へ向かわせたのです ところが!松前藩はこの桜井をすぐさま斬り捨てたのです 松前藩の考えは「新政府軍は近いうちに絶対蝦夷地へやってくる。旧幕府軍の味方なんかしちゃったら大変なことになる」というものだったのです |
| 10月28日 土方 松前へ向かう |
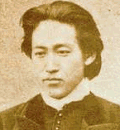 徹底抗戦を宣告してきた松前藩 徹底抗戦を宣告してきた松前藩旧幕府軍は、すぐさま軍を差し向けることに このとき大将となったのが土方歳三でした こうして、土方率いる旧幕府軍が、松前まで100キロの道を進軍することになったのです この進軍は、とてもゆっくりとしたものでした 彼らには「ゆっくり進軍している間に、松前藩の考え方が変わってくれるかもしれない」というものだったのです |
| 11月1日 土方 松前藩を蹴散らす |
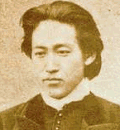 が、そんな彼らの思いは通じませんでした が、そんな彼らの思いは通じませんでしたこの日、松前藩士らが、野営をしている土方らを襲撃してきたのです 突然の敵襲に驚いた土方軍でしたが、敵のたいまつの数を見て「これは少人数だな」と察知 すぐさま反撃に出たのです この奇襲はあっけなく終わり、松前藩士たちは逃げていったのでした その後も松前藩は、なんとしてでも土方軍を阻止しようと色んなとこから攻撃してきますが、そのたびに土方の的確な指示により敗北 もはや土方は刀で斬り込む新撰組時代の土方ではなく、近代化の兵法によって敵と戦う男になっておりました |
| 11月5日 松前藩 落城 |
こうして土方軍はどんどん進軍し、この日の朝、福山城下に到着 対する松前藩は大砲を用意し、何とか土方軍をやっつけようとしました ちなみに・・・・福山城の裏手にはお墓がありました 松前藩の敵は今までアイヌの人々しかいなかった アイヌの人たちは決して墓を踏み荒らすようなことはしないというルールがありました ところが土方軍は墓地に遠慮などしない 手薄になった墓地側からも攻めてきたのです もちろん松前藩も必死に抵抗しましたが、実戦慣れしていない松前藩と今まで戦い続けてきた土方軍では差は歴然 とうとう松前藩兵たちは逃げ出していったのです こうして土方軍は松前藩の本拠地である福山城下を占拠したのでした |
| 松前藩主 逃げちゃいました |
ところで、松前藩主の徳広(のりひろ)はというと・・・・ 実は!土方軍が五稜郭から出た時、すでに逃げてました しかも家の人たちには「温泉に行って来る」とまで言ってました 逃げた先は、現在作りかけのお城であります で、福山城を奪われた松前藩の人たちは、藩主が逃げ込んだ新しいお城と、要塞がある江差と、二つに分かれて逃げておりました この新しいお城には200人ほどが立て籠もってたんですが、11月15日に攻撃されちゃいます このときも、藩主徳広は激戦のドサクサに紛れ逃げていきました が、逃亡中にあまりの寒さに具合が悪くなり危篤状態に そしてとうとう、11月29日は死んでしまったのです まだ25歳の若さでした 松前藩は体裁が悪いってことで、新政府に「病死」とは言わず、旧幕府軍に敗北したことに対する責任を負った自刃と報告したのでした |
| 土方軍 江差をゲットする |
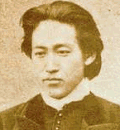 土方軍は、要塞のある江差へ進軍していきました 土方軍は、要塞のある江差へ進軍していきましたここでは氏家丹後率いる松前藩士が、なんとしても侵入を防がねば!!と、必死の抵抗 ここで土方の策略が 土方はわざと大苦戦しているフリをしたのです 松前藩士たちは「敵が苦戦している!!もう少しで勝てるかもしれない!!」と、集結しまくり その時、後ろから旧幕府艦隊が姿を現し、松前藩士たちを挟みうちにしたのです これにはさすがにビックリ とうとう、抵抗することをあきらめ、旧幕府軍に降伏したのでした |
| 11月15日 江差湾で軍艦 開陽丸が座礁する |
江差を占領し、完全に蝦夷地を制圧した旧幕府軍 が、ここで大ショックなことが起きてしまうのです この日、江差にやってきた開陽丸が暴風雨のため座礁してしまったのです 榎本武揚は開陽丸命!!な男だった 何とかして開陽丸を・・・と、他の二つの「回天」と「神速」を使い、岩礁から開陽丸を引っ張り出そうとしたのです が、暴雨風はさらに激しくなり、なんと「神速」までもが沈んでしまったのです 「開陽丸」と「神速」を失ったことは、旧幕府軍にとって大打撃となり、さらには士気も下がっていくこととなってしまいました 榎本武揚と土方歳三は、沈み行く開陽丸を見て男泣きしたといいます |
| 英仏 「デ・ファクトの政権」 |
さてさて、福山城をゲットした後すぐに、イギリスとフランスの艦隊が箱館にやってきました そして両国は、蝦夷政権を「デ・ファクト政権」として承認するといったのです 「デ・ファクトの政権」というのは、事実上の政権として認めるということ ということで、イギリス・フランスは、日本の国内問題には中立でいるということになったのでした こうして、旧幕府脱走軍は、事実上蝦夷の権利を握る政権として、各国から容認され、謀反人の集団ではないということに この時、榎本武揚がイギリス・フランスの両艦長に明治政府への手紙を託しました その内容は 「私たち徳川旧家臣は、三十万人以上います。 それが、七十万石という領地になってしまっては、皆飢え死にしてしまいます。 ですから、この蝦夷地を私たちに譲っていただきたいのです。 それが許可されれば、旧家臣たちを呼びよせ、原野を開拓し、朝廷のために北側の警備をしたいと思っています。 箱館府との激突は、清水谷府知事のもとへ嘆願に行ったところ、早々に賊の悪名をつけられ、仕方なく応戦したのです。 また、蝦夷地に徳川の血筋の方を一人送ってください そうすれば、私たちはますます奮発し、朝廷への忠勤にはげみます。 第一に朝廷のため。第二に徳川のためどうか、この願いをお聞き届けください」 |
| 12月15日 蝦夷政権誕生 |
 この日、投票によって新政権の役職が選ばれました この日、投票によって新政権の役職が選ばれましたこの投票システムは、榎本武揚が発案 彼は留学経験があり、諸外国を見てきたことから、このような方法が考えついたのです といっても、投票の権利があるのは、3500人に及ぶ脱走軍のうち、士官クラス800名 で、投票結果は・・・ 榎本武揚 156票 松平太郎 120票 永井尚志 116票 大鳥圭介 86票 土方歳三 73票 といった感じであります この選挙結果によって、榎本武揚が総裁に 副総裁は松平太郎 そして箱館奉行は永井尚志 陸軍奉行 大鳥圭介・土方歳三 以上が決められ、蝦夷平定の祝賀会が五稜郭で開かれたのです 停泊中の軍艦からも祝砲が放たれ、箱館始まって以来の賑わいとなりました |
| この年のおもな出来事 |
・9月23日 横浜では「立小便禁止」となる。外国人が多い横浜では、日本人の作法を正しくしようということになりました ・11月7日 医者が開業するには、免許がなければダメという布令が出ました ・11月9日 築地ホテル開業 プリッジンスが設計し、清水屋喜助が工事を請け負いました この清水屋はのちの清水建設になります ちなみに客室は102室で、宿泊料は一日3ドル ・東京に初めて牛鍋店ができる もともと中川屋嘉兵衛が、慶応3年に牛肉屋を開業してたんだけど、堀越藤吉がこの権利を譲り受けた で、初めて「御養生牛肉」と書いた看板をかかげた ・風月堂がパンを焼きだした。持ち運びが便利なので薩摩藩では戊辰戦争の時の携帯食に採用 ・官軍側で、人の肉を三杯酢にして食べるとおいしいという噂が広がり、実際食べたらしい ・ハワイへ120人が契約移住民として渡航しました ・小倉虎吉という人が、横浜で外国人専用の理髪店を開業 ・江戸では生活に困った下級武士たちが骨董屋や露天商を開いて食いつなぐ状況が多発 |